
出産を終えた後、同じく今後妊娠・出産を考えている友人から聞かれる質問が「陣痛どうだった?」と同じくらいの割合で「いくらかかった?」「どれくらいお金あったらいい?」でした。無痛分娩を希望するかどうかや、都内なのか地方なのかなど、個人差がかなり出てくるとは思いますが、経験談も踏まえてまとめていきたいと思います。

もしもの時の備えとして、貯金はとても大切
- 結論:貯金はあればあるほど安心。
節約上手な方は50万で大丈夫。多くの方は100-150万あると安心。
東京でグッズにこだわりたい方は200-300万がオススメ。 - 1.はじめに
・妊娠と出産は「保険診療ではなく、自費」
・「自費診療」のため、費用は地域差がかなりある - 2.妊婦健診には思ってたよりお金がかかる
・早く病院に行くのは少し勿体無い?
・合計大体10〜15万ほどかかります - 3.病院の規模と場所によって基本的な分娩費用が大きく変わる
・東京都か、それ以外か
・個人経営の産院か、大規模な病院か - 4.無痛分娩や個室を希望するかで費用が変わる
・麻酔費用も少し地域差がある - 5.赤ちゃんグッズは節約しても消耗品にお金がかかる
・お下がりを譲ってもらっても基本的に結構かかる
・初節句などのイベントを忘れずに - 6.育児休業給付金でやりくりできる?
・産休に入る前に家計を見直して不足分を把握しよう - 7.里帰りやリフレッシュにかけられるお金も確保すべき
・メンタルケアにはお金を使うべき - まとめ
・夫婦で自分たちの出産についてかかるお金を試算して話し合っておくとクリアに
結論:貯金はあればあるほど安心。

都内は200〜300万がオススメ。
地方の場合は100〜150万でも大丈夫かもしれません。

ここまで必要ない方が大半かもしれませんが、念の為のお金なので多めに書いています。
理由は下記で詳しく書きますが、自分が妊娠・出産前に計算していたお金よりも、実際の費用は結構かかってしまったのと、「もっとこれくらいあればメンタルが楽だったかな」と感じた部分があるからです。
1.はじめに


知人から「高額療養費制度は使えないの?」という質問もありましたが…
・妊娠と出産は「保険診療ではなく、自費」
そもそもとして、妊娠出産は自費診療になります。とはいえ、妊婦健診には自治体から『助成金(券)』が貰えますし、健康保険から『出産費用一時金』が出るので、自己負担はかなり抑えられます。
・「自費診療」のため、費用は地域差がかなりある
やはり東京は一番高く分娩費用は平均で「60万前後」、安い県だと「37万ほど」だそうです。(2025年時点)
全国平均では2023年時点で「50万円前後」となっています。(東京はなんでも高いですね…涙)
2.妊婦健診には思ってたよりお金がかかる


初の診察は急ぎすぎても意味がなかったです涙
・早く病院に行くのは少し勿体無い?
こちらは完全に自分のミスなのですが、早めに分かる市販の検査薬で陽性が出た後すぐに病院で診察を受けたのですが、行ったタイミングが早すぎて「二週間後にまた来てください」と言われ、しかししっかり1万の自費を払って帰ったという失敗談があります…(涙)早すぎると胎児を確認ができないそうなので、早すぎず、遅すぎずのタイミングで受診することをお勧めします。
・合計大体10〜15万ほどかかります
自分の場合は上記のフライング診察含め、14万ほどかかりましたが、最後は予定日より早く産まれたため、健診を1回か2回スキップしています。そのため、通常通りだと15万くらいにはなりそうです。
自治体から助成券を貰っていたのですが、それを使っても毎回1万近くかかるので、毎回会計のたびにビクビクしていました。
妊婦健診費用想定:15万
3.病院の規模と場所によって基本的な分娩費用が大きく変わる

・東京都か、それ以外か
東京は全国平均で最も分娩費用が高い場所です。全国平均は2023年の時点で約50万ほどのようですが、東京は平均60万。逆に費用が安い県だと、40万を下回るところもあるようです。出産を考えている地域の分娩費用を調べてみることをお勧めします。
ただ、『出産育児一時金』として50万円が貰える(2025年時点)ので、そちらも考慮して検討してみてください
・個人経営の産院か、大規模な病院か
自分の出産の際に都内の(無痛分娩ができる)産院をいろいろと調べたのですが、大学病院などの規模が大きな病院の基本的な分娩費用は85万が中央値の印象でした。大規模ではない産院の分娩費用は50〜60万が多かったです。
妊婦健診費用想定:15万
+基本分娩費用:50万(出産育児一時金で50万もらえるので実質0円)
4.無痛分娩や個室を希望するかで費用が変わる

麻酔は個人的には本当に選んでよかったです。陣痛痛すぎました….
無痛分娩を希望する場合は、約10〜20万ほどかかります。こちらも値段は地域や病院によって様々です。
また、入院期間は5-6日ほどになるかと思いますが、大部屋なのか、個室にするのかで追加料金が発生します。個室の場合の多くは、旅行でよくある「一泊二日」の料金ではなく「一日あたりいくら」なので、5泊6日の場合『×6』となります。こちらも出産する産院の個室のグレードによります。数千円から数万円と、その差は様々です。個人的には、産後というとてもデリケートな時間なので、個室代を奮発して出してよかったな、と思いました。
ここでは無痛分娩希望、個室希望の想定で計算しておきます。
▼分娩費用は全国の平均的な費用を想定して計算
妊婦健診費用想定:15万
+基本分娩費用:50万(出産育児一時金で50万もらえるので実質0円)
+麻酔費用:15万
+個室料金:6万
5.赤ちゃんグッズは節約しても消耗品にお金がかかる


可愛いベビーグッズ、揃えたいですよね…
・お下がりを譲ってもらっても基本的に結構かかる
産院と違って、このベビーお迎えグッズにかける費用は、夫婦で最も調整がきく部分かと思います。ただどう頑張っても、消耗品類や最低限のベビーグッズは購入する必要があるので、どうしても費用はそれなりにかかってきます。
しかも可愛いベビーグッズが世の中にはたくさんあるので、せっかくなら可愛いもので揃えたい!という方もいらっしゃるかと思います。
①こだわりのグッズを金額問わず全て揃えたい!….約30万
②ベッドなどの大型は譲ってもらいつつお気に入りを揃えたい!….約20万
③必要なものをそれなりに買い揃えたい!….約10万
④ほぼ譲ってもらえる想定で、服や消耗品系のみ揃える!…約5万
自分はベビーベッド、バウンサーを譲ってもらったのですが、それでも20万ほどかかりました。やはり可愛いベビーグッズを揃えたい欲には勝てませんでした。大型の費用はほとんどかかっていないのですが、それでも結構するなぁという印象でした。(振り返ると要らなかったものも多くありますが…笑)
▼全国の平均的な費用を想定して計算
妊婦健診費用想定:15万
+基本分娩費用:50万(出産育児一時金で50万もらえるので実質0円)
+麻酔費用:15万
+個室料金:6万
+ベビーお迎えグッズ:15万(個人差大)

忘れてはいけないのが赤ちゃんのイベントにかかる費用です
・初節句などのイベントを忘れずに
お宮参り、お食い初め、初節句、ハーフバースデーなど、赤ちゃんのお祝いイベントは沢山ありますし、ちゃんとお祝いしたいですよね。写真館で撮影したりするのも楽しそうです。こちらのイベント費用も計算に入れておくことをお勧めします。やり方によっては費用を抑えられますが、思い出になるものなのでここは頑張りたいところです。
▼分娩費用は全国の平均的な費用を想定して計算
妊婦健診費用想定:15万
+基本分娩費用:50万(出産育児一時金で50万もらえるので実質0円)
+麻酔費用:15万
+個室料金:6万
+ベビーお迎えグッズ:15万(個人差大)
+ベビーイベント事:10万(個人差大)
6.育児休業給付金でやりくりできる?

ここの計算はとても大事です!
・産休に入る前に家計を見直して不足分を把握しよう
「赤ちゃんのために払うお金」に気を取られがちですが、そもそも自分の生活費を正確に把握できていますか?産休・育休に入ると、『育児休業給付金』という給付金がいただけるのですが、今までのお給料の全額ではなく、『標準報酬月額の67%』『180日すぎたら50%』のみの支給となります。
社会保険料など、税金は免除されるので、実質の手取りは「標準報酬月額の80%程度」になりますが、忘れてはいけないのが『住民税』です。この税金は特殊で、「前年度の年収に対する住民税」を払うことになるため、感覚的には後払いシステムのようになっています。結構ここを失念している方が多いのかなとも思います。
そのため、「手取りが80%ならギリギリ大丈夫かも」と思っていたら、住民税を支払ったら赤字になってしまった、という事もあり得るわけです。
給付金の「手取りの80%(180日まで)」をそれまでの月の生活費が超えてしまっている場合は家計を見直ししたり、不足分をカバーできる貯金を持っておき、前年度の住民税はそれまでの年収にもよりますが、貯金して取っておくことをオススメします。
年収400万くらいの場合は、地域差もありますがおおよそ20万見ておけば大丈夫そうです。
▼分娩費用は全国の平均的な費用を想定して計算
妊婦健診費用想定:15万
+基本分娩費用:50万(出産育児一時金で50万もらえるので実質0円)
+麻酔費用:15万
+個室料金:6万
+ベビーお迎えグッズ:15万(個人差大)
+ベビーイベント事:10万(個人差大)
+生活費不足分:12万(月1万の想定/個人差大)
+住民税支払い分:20万(前年度の年収による)
7.里帰りやリフレッシュにかけられるお金も確保すべき


産後と育児中は、ホルモンバランスの乱れでかなりメンタルが乱れます
・メンタルケアにはお金を使うべき
こちらは声を大にして伝えたいのですが、産後・育児中のメンタルケアは本当に大切です。初めての育児、壮絶な出産とそのダメージ、完全に変わる生活リズム、産後のホルモンバランスの急激な変化で、生理前後の心身の不調とは比べものにならないほどのメンタルの揺さぶりがやってきました….!
ホルモンのせいだと頭では分かっていても、どうしようもないものです。
ここでさらに『リフレッシュしたいけどお金がない』となってしまった時には、精神的にさらなる負荷がかかってしまいます。
私自身は計算よりも十分な貯金を用意したつもりだったのですが、産後に急激な焦燥感に襲われました。数ヶ月たつとホルモンバランスも落ち着き、「なぜあの頃あんなに不安で焦っていたんだろう」と冷静になれましたが、本当に産後のメンタル不調は侮れません。
生後3ヶ月くらいになると予防接種も打てており、産後の体も軽いお出かけなら問題なくできるようになっている方が多いと思うので、その際に『お金がないからリフレッシュを我慢しよう』としてメンタルを悪化させるよりは、『このための貯金だ!』と割り切って使って楽しむくらいが良いと思います。
▼分娩費用は全国の平均的な費用を想定して計算
妊婦健診費用想定:15万
+基本分娩費用:50万(出産育児一時金で50万もらえるので実質0円)
+麻酔費用:15万
+個室料金:6万
+ベビーお迎えグッズ:15万(個人差大)
+ベビーイベント事:10万(個人差大)
+生活費不足分:12万(月1万の想定/個人差大)
+住民税支払い分:20万(前年度の年収による)
+リフレッシュ代:20万(個人差大)
まとめ

ざっくりですがまとめると….
①分娩費用を全国平均の50万で計算し、リフレッシュにもベビーグッズにもお金を使いたい場合
妊婦健診費用想定:15万
+基本分娩費用:50万(出産育児一時金で50万もらえるので実質0円)
+麻酔費用:15万
+個室料金:6万
+ベビーお迎えグッズ:15万(個人差大)
+ベビーイベント事:10万(個人差大)
+生活費不足分:12万(月1万の想定/個人差大)
+住民税支払い分:20万(前年度の年収による)
+リフレッシュ代:20万(個人差大)
=合計113万

麻酔を希望する場合は現実的なラインかなと思います!余裕を持って150万くらいあると◎
②分娩費用50万で計算し、麻酔はせず給付金内でやりくりを頑張った場合
妊婦健診費用想定:15万
+基本分娩費用:50万(出産育児一時金で50万もらえるので実質0円)
+麻酔費用:0万
+個室料金:0万
+ベビーお迎えグッズ:5万(個人差大)
+ベビーイベント事:5万(個人差大)
+生活費不足分:0万(月1万の想定/個人差大)
+住民税支払い分:20万(前年度の年収による)
+リフレッシュ代:0万(個人差大)
=合計45万

かなり節約を頑張った場合です。ベビーグッズをほぼ譲ってもらうことが条件になります。
③分娩費用を東京/大病院の85万で計算し、リフレッシュにもベビーグッズにもこだわりたい場合
妊婦健診費用想定:15万
+基本分娩費用:85万(出産育児一時金で50万もらえるので実質35万)
+麻酔費用:20万(大きな病院の場合20万のところも)
+個室料金:10万(個室代は大きな病院ほど上限が広い)
+ベビーお迎えグッズ:30万(個人差大)
+ベビーイベント事:15万(個人差大)
+生活費不足分:12万(月1万の想定/個人差大)
+住民税支払い分:20万(前年度の年収による)
+リフレッシュ代:20万(個人差大)
=合計192万
(東京都の場合、赤ちゃんグッズのチケットが10万円分もらえるのですが、計算がブレるので一旦なしで書いています)

200万あれば大丈夫ですが、ベビーグッズを買い増ししたり、旅行に行くなら300万あると◎
いかがでしたでしょうか?個人的なオススメは『焦らなくていいように夫婦で貯金200万』です。
お金に関する焦りがメンタルに悪影響を及ぼすことをなるべく避けられると良いかなと思います。
家計ややりくりのことなど、事前に夫婦で話し合って計画を立てておくことをオススメします!
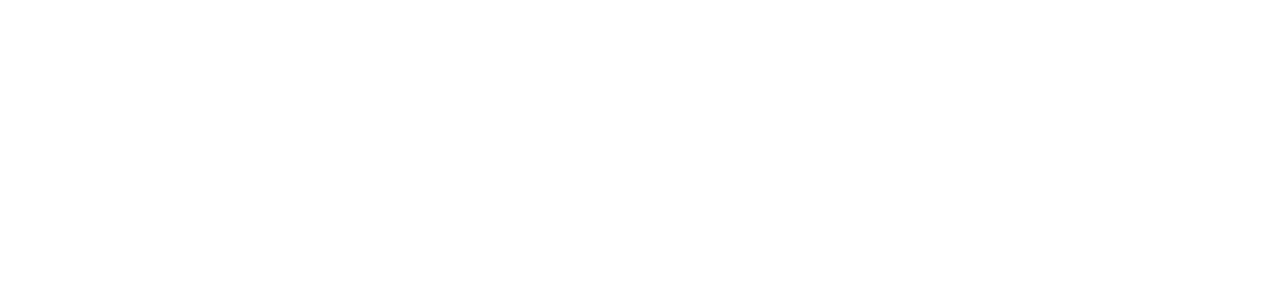






コメント